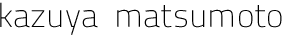
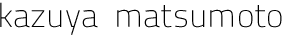

「滲みの際を知覚する」
“ちょっとすみません、自分の手を目の前にかざしてみてほしいのですが。
手のひらが見えますよね。それはあなたの手ですね。
もうちょっとだけすみません、その手でどこか自分のからだを触ってみてもらいたいのですが。
そうですね、右利きの人は左の肩に右手を、左ききの人は右の肩に左手をのせていただくなどいいかもしれません。
はい、あなたの手とあなたの肩が接触しましたね。
そこでお尋ねしたいのですが、
今、あなたの手が肩に触れているのですか?
それともあなたの肩が手に触れられているのですか?”
『水のかたち』には、間違いなく松本一哉の演奏が収められている。彼のライヴを見たことがなくても、注意深く聴けば、楽器の音と周囲の環境音を識別するのは特に難しくない。
一方で、環境が鳴らす音は、天候や温湿度、時間帯、その場の生態系など、さまざまな要因が結晶化した偶然の産物である。そこに演奏家は立ち会うことはできても、関与することはできなかったはずだ。
それらが入り混じって収録されたこの音源集を、それでも松本の作品だと見留めることができるのはなぜか。それは普段から私たちが、主体と客体の溶融や境界の消失といった観念的な経験を、それとは気付かずに身体知として会得しているからなのではないかと思考してみたい。まわりくどい言い方でほんとすいませんなのだが、この作品を「フィールド・レコーディング」に止めず、松本の言う「偶然のオーケストラへの参加」として追体験するためにも、こういう込み入った考察には惜しまず臨んでみる方が、断然面白くなると思うのだ。
車を停めて機材を降ろす。湿った枝を踏みしめながら奥へ奥へと歩を進め、充分に木々の深くまで潜ったと思えたところで足を止める。材質や形状のさまざまな音具を取り出し、それらを厳粛な手つきで地面に配置する。慎重にマイクの位置を整えてRECボタンを押したら、ふうっと息を吐き、首をうなだれて目を閉じる。
耳は鋭敏になり、静寂に満ちていたはずの周囲が微細な鳴動をはじめる。暗闇に目が慣れるのと似た速度で、聴覚は指数関数的に解像度を増していく。やがて、ざわめきと身体の境界は消散し、自分と環境との区別がつかなくなる。音は拡散しているのか。それとも浸透しているのか。今この身体は発振器なのか。受容器なのか。
この作品は、音楽家によるフィールド・ドキュメンタリーを越えた、知覚への挑発である。松本一哉は自然との共演を通じて、意識と実存の更新に挑もうとしている。
水のかたちを再生する。
聴こえてるのか聴いてるのか。
色々と鳴ってる音があるんだけど、その、あるってことは難しくて、大好物なので、起こることが再生されるたびに感触とか形が伝わってくる。
生きものの記録。
で、自然ってなんなんだろう、ほんとうってなんだろう。
触れるんだとおもいます。生まれてきたから。
鳴ることで生まれてくるものが発する気配のなかに松本さんがいる。愉快です。
均一化された単純なフィールドレコーディングではない、何がおもしろい音で、何がこうふんする音か、伝わります。
耳を練成しながらRECし続けた Kazuya Matsumoto の半生じゃないでしょうか。
いよいよのリリース、おめでとう。
波の音、雨の音、洞窟の中の水流の音、録音する事によって形を与えられた自然の音、様々な打楽器の音、水と金属と天然の残響。
ここにある全ての音がお互いの存在を邪魔する事なく調和している。
松本一哉は自然をチューニングする魔術師だと思う。